『ブラックフット』(アダム・マクドナルド監督/2014年)
👉『ブラックフット』(Amazonページ)
内容紹介と感想
本作は、2005年にカナダ・オンタリオ州で実際に起きた熊の襲撃事件に着想を得て制作された “実話ベースのフィクション” である。
事件そのものの詳細は記事の後半〈ネタバレあり〉で触れるが、映画はその出来事を下敷きに、カナダのバックカントリーで道に迷い、熊と遭遇するカップルの不安と恐怖を描き出している。
ただし、単なる“動物パニック映画”とは異なり、カップルの関係性やそれぞれの内面も丁寧に描いている点が大きな特徴だ。
また、湖や森の自然、カヌーでの移動、森を歩く足取り、焚き火やテント設営といったアウトドア・アクティビティの描写も実にリアルで、まるで自分自身がハイキングしているかのような没入感が味わえる。アウトドアが好きな人なら、きっと惹き込まれるだろう。
見事な自然描写や繊細な心理描写、じわじわと迫ってくる孤立感・不安感・絶望感、そして迫力とリアリズムに満ちた熊との衝撃的な遭遇シーン──そのすべてに引き込まれ、最後まで没頭して見ることができた。
映画は、カップルが車で人里離れた森のキャンプ地に向かうところから始まる。早くも旅に出ているような感覚を味わえる導入だ。
カップルは目的地に到着すると、観光案内所でカヌーを借りることになる。その道中や、案内所周辺でのやり取り――車内での何気ない会話や表情の変化、ちょっとしたトラブルへの対応などから、少しずつ二人の人間関係や性格が浮かび上がってくる。
映画が始まって10分ほどで、「この二人はどんな関係なんだろう?」「これから何が起こるんだろう?」と、自然と引き込まれていく。
やがて森での最初のキャンプ中、地元でガイドをしているという男が現れ、夕食を共にすることに。だが、彼の言動にはどこか不穏な空気があり、カップルの間にも微妙な緊張が走る。互いの判断を信頼しきれず、ぎこちない空気が流れ始める。
「もし自分だったら、どう対応するだろうか」――そんなふうに考えさせられながら、不安感がじわじわと高まっていく。
このあたりから、心理描写に優れた監督の手腕が際立ち始め、「ただのアニマルパニック映画ではない」と感じさせられるようになる。

その後も、地図がなくても道はわかると自信を見せる男性に対して、女性が見せる信頼と不安、そして喧嘩をしながらも互いに寄り添おうとする関係性が、じわじわと描き出されていく。
こうした丁寧な心理描写によって、観る側はいつのまにか二人の気持ちに寄り添い、感情移入していく。
だからこそ、物語が後半に入り、二人が森の中で道を見失っていく場面では、強まる不安感がよりリアルに伝わり、さらには熊との遭遇によって生じる恐怖までもが、より深く心に迫ってくる。
熊との遭遇に関しても、いわゆるホラー映画にありがちなジャンプスケア的な演出ではなく、痕跡や気配が少しずつ現れ、熊が静かに、じわじわとカップルに近づいてくるような描写が続く。
ここではネタバレを避けるが、やがて訪れる直接的な遭遇のシーンは、まるでドキュメンタリーを見ているかのようなリアリズムと衝撃があり、息を呑まずにはいられなかった。
その描き方について、米アウトドアメディア「Outside Online」では、「ブラックベア襲撃の実例データを踏まえた極めてリアルな描写」と紹介されている。
どんなシーンかの詳細は控えるが、“実際に起こり得る恐怖” を体感できることだけは伝えておきたい。(※具体的な統計や証言は、次の〈ネタバレあり〉の章で解説。)
また、アウトドア好きな方にとっては、サバイバルの “心構え” という意味で学びの多い作品でもある。
とくに男性主人公の不注意や油断が目立ち、「こういうときはこれを持っていくべき」「ここにはもっと注意が必要だ」といった具体的な意識を自然と喚起される。
映画全体として、決してアクションに重きを置いた作品ではなく、あくまでスローペース。だがそのぶん、頭と心が激しく揺さぶられるような、内面的なドラマが際立っている。
観ていて思い出したのが、ケリー・ライカート(Kelly Reichardt)監督の作品群だ(※この記事の最後にある “関連しておすすめの映画” の章もぜひ参照してほしい)。
彼女の作品は、テーマや物語の展開以上に、登場人物がその瞬間に何を感じているか――その「心の動き」を丁寧に描き出す点に真骨頂がある。だからこそ、観ている側も心理的に濃密な時間を過ごすことになる。
本作『ブラックフット』もまた、極端に言えば熊との遭遇シーンがなかったとしても、その閉ざされた自然と二人の関係性が織りなす空気感だけで、十分に作品世界に浸ることができるように思えた。
👉『ブラックフット』(Amazonページ)
具体的な内容・感想(ネタバレあり)
上述の通り、本作は森の中でのサバイバルの側面で、反面教師的な視点からも見ごたえがあった。
とにかく、男性主人公の軽率さが目につく。過去に訪れた場所だからと油断し、地図を持たずに出発し、携帯電話は車内に置きっぱなし、食料も充分とはいえない量しか持参していない――という具合だ。
加えて、熊の襲撃シーンをはじめ、足を骨折したり深手を負ったりといった生々しい負傷描写も多い。
そうした場面を目にすると、あらためて「自然に入るときは、備えを万全にして臨まなければ」と気が引き締まる。その意味でも、ハイキングや森林に入る機会のある人には、ぜひ一度観てほしい作品だ(むしろ自然が怖くなってしまうかもしれないが…)。
とはいえ、アメリカやカナダの田舎では、「ちょっと近くでハイキング」といった感覚でも、その自然の規模や “手つかずの森林感” がとんでもないレベル、ということが本当にある。
少しハイキングルートを外れただけで、まるで本物の原生林に迷い込んだような感覚になるし、人の来ない場所で道を失えば、冗談抜きで取り返しのつかない事態にもなりかねない。
北米には、そうした “真の大自然” と向き合わされるような場所があちこちにある。だからこそ──もちろんこの男性主人公の油断を擁護するわけではないにせよ──「知ってるところだから」と軽い気持ちで入り込み、気づけば戻れなくなる、ということが現実にもそこそこあるのだろうな、という気もしてしまうのだ。

熊の襲撃シーンは、まるでドキュメンタリーを見ているかのような生々しさに満ちており、痛みと苦しみがひしひしと伝わってくる。
それは、熊の映像が派手に演出されているからというよりも、あくまで “現実に起こりうる感触” に根ざした凄みによるものだと感じた。
たとえば、男性の顔半分の皮膚が剥がれ、もがき苦しむ姿は、もはやホラー映画の枠を超え、“現場” に立ち会ってしまったかのような不快感と衝撃を残す。「ものすごく嫌なものを見てしまった……」という感覚と同時に、妙な現実味が後を引く。
とりわけ、これまでの描写を通して、男性の未熟さや弱さを感じながらも、どこか人間味に惹かれ始めていたからこそ、その最期は胸に迫るものがあった。
「嫌なものを見た」といいつつ、映画としては非常に見応えのある、印象的なシーンだったと言えるだろう。
アウトドア系メディア「Outside Online」の記事によると、ある研究(1900~2009年の事例を分析)から以下のような傾向が報告されている。
- ブラックベアによる致命的な襲撃の約70%は日中に発生しており、特に8月に集中していた。
- 生存者がいたケースの95%では、熊がすでに50メートル以内まで接近してからようやく存在に気づいたとされる。
- 複数人が一緒にいた場合でも、熊は一人を襲って遺体を引きずり去り、場合によっては同じ熊が後に戻って再び襲撃することもあった。
アダム・マクドナルド監督は、こうした実際のデータや被害者の証言を参考に、熊の動きや襲撃時の感覚を忠実に再現しようとしたという。
「熊はゆっくり静かに近づき、襲撃そのものは一瞬で起こる。多くの生存者が “突然音が消えた” “耳鳴りや破裂音のようなものがした” “何が起きているのかわからなかった” と語っている。それらすべてを映画に盛り込み、観客がその場にいるかのように感じられるよう意識した」と監督は語っている。
こうした背景を踏まえると、『ブラックフット』の熊襲撃シーンは、演出としての迫力だけでなく、実際の事例に基づいたリアリズムの点でも秀逸だと言えるのではないだろうか。
冒頭でも触れたとおり、本作は2005年9月6日、オンタリオ州ミシナイビ湖州立公園で実際に起きたブラックベア襲撃事件(被害者はDr. Jacqueline Perry、夫のMark Jordan)に着想を得ている。
実際の事件では、テント設営中に妻が熊に襲われ、森へ引きずり込まれかけるが、夫がポケットナイフ(スイスアーミーナイフ)で応戦し、熊ともみ合いながら繰り返し突き刺してようやく妻を解放させた。
夫は自らも傷を負いながら、なお背後から迫る熊に追われつつ、妻をカヤックに乗せて移送した。だが、残念ながら妻は搬送中に命を落とした。
ジョーダンはこの行為によりStar of Courageを授与されている。映画はこの出来事を土台にしつつ、人物像や出来事の細部をフィクションとして再構成している。

僕自身、アメリカやカナダでハイキング中に熊に出くわしたことが何度かある。いずれもある程度距離が離れていたうえに、周囲には他のハイカーもいたため、それほど恐怖を感じることはなかった。
だが、もしそれが誰もいないバックカントリーで、しかも道に迷っている最中だったとしたら――想像するだけで、心の底から絶望的な気分になる。

『ブラックフット』(原題:Backcountry)海外版ポスター画像(© 2014 Fella Films):個人的には、こちらの方が「熊がじわじわと迫ってくる」この映画の空気感によりよく合っている気がする。
👉『ブラックフット』(Amazonページ)
関連しておすすめの映画
『オープン・ウォーター』(クリス・ケンティス監督/2003年)
ニューヨーク・タイムズ紙の記事によると、本作『ブラックフット』を手がけたアダム・マクドナルド監督は、制作にあたり “森の『オープン・ウォーター』” という発想が出発点にあったと語っている。
映画『オープン・ウォーター』では、スキューバ・ダイビングに出かけたカップルが、グループに置き去りにされ、広大な海に取り残されてしまう。やがて彼らの周囲には、サメの影がじわじわと現れ始め、逃げ場のない絶望的な状況に追い込まれていく。
サメそのものを前面に押し出したパニック映画とは異なり、本作は終始、極めて現実的なトーンで描かれているのが印象的だ。
サメ描写は決して派手ではないものの、ふとした瞬間に海中でサメの体に触れてしまったかのような、ざらりとした質感が伝わってくる。その感覚は、じわじわと神経を締めつけるような、言葉にしがたい恐怖を呼び起こす。
広大な海の “底知れぬ恐怖” を全身で体感できる、静かで強烈な一作である。
👉『オープン・ウォーター』(Amazonページ)
『127時間』(2010年/ダニー・ボイル監督)
また、『ブラックフット』のように、「よく知っている場所だから」という油断から、十分な準備もないまま大自然に踏み込み、取り返しのつかない状況に陥ってしまう──そんな“実際に起きた事故”を描いた作品として、『127時間』もあわせて紹介したい。
舞台はアメリカ・ユタ州。青年が渓谷でキャニオニングを楽しんでいた際、落石により腕を挟まれてしまう。何度も訪れた場所という油断から、家族や友人にも行き先を知らせず、飲料水などの備えも十分ではなかった。
そうして誰にも気づかれぬまま、孤独と絶望の中に取り残される──本作は、そんな極限状況の中での人間の心理と自然の恐ろしさを、丹念かつ濃密に描いている。
👉 『127時間』(Amazonで見る / 当ブログのレビューを読む)
こうした「恐怖」の描写もさることながら、『ブラックフット』の本質は、極限状況の中で静かに削られていく心理描写にあるように思う。
そうした感覚は、動物パニックという枠を超えて、たとえば上で紹介したケリー・ライカート監督作品のような、“静かだけれど心の中は騒がしい”映画にも通じるものがある。
(ジャンルはまったく異なるが)そうした“心の奥に入り込んでくるような作品”を、以下に2本紹介したい。
『ナイト・スリーパーズ ダム爆破計画』(ケリー・ライカート監督/2013年)
過激な環境保護活動家が、水力発電ダムを環境破壊の象徴とみなし、爆破を計画するというストーリー。
日本語のタイトルやあらすじだけを見ると、手に汗握るアクション映画を想像するかもしれないが、実際には、主人公の心の揺れを静かに追いかけていく作品だ。その意味では、原題の『Night Moves』の方が、この映画の余韻や空気感をよく表しているように感じる。
観ているあいだ、主人公が抱える罪の意識や、いつ警察に見つかるかわからないという不安感が、観客の側にもじわじわと染み込んでくる。
👉『ナイト・スリーパーズ ダム爆破計画』(Amazonページ)
『ウェンディ&ルーシー』(ケリー・ライカート監督/2008年)
本作では、女性主人公が犬を連れてアラスカを目指す旅の途中、オレゴン州の小さな町に立ち寄る。そこで車は故障し、犬も姿を消し、まさに踏んだり蹴ったりの出来事が続く。
特別にドラマチックな展開があるわけではないが、主人公の抱える不安や孤独がひしひしと伝わり、見ているこちらまで胸が締めつけられるような気持ちになる。
どんな感情であれ、登場人物の内面を丁寧に描き出す作品は、やはり心に残るものだ。
👉『ウェンディ&ルーシー』(Amazonページ)
──────────────────
📖関連記事
👉 『羆風(ひぐまかぜ)』感想:どれくらい怖いのか──三毛別熊害事件と開拓地の現実
北海道の三毛別熊害事件をもとにした漫画『羆風(ひぐまかぜ)』をレビュー。どんな怖さが描かれているのか、その恐怖の質と熊の視点、開拓地の暮らしまでを丁寧に考察。
『羆風(ひぐまかぜ)/飴色角と三本指』(Amazonページ)
👉『生物学探偵 セオ・クレイ 森の捕食者』感想|熊の襲撃をめぐる生物学ミステリー
熊の襲撃をめぐり、主人公が科学的手法で真相にじわじわ迫るミステリー。モンタナの大自然とスモールタウンの空気が濃く立ち上がる一冊。
『生物学探偵 セオ・クレイ 森の捕食者』(Amazonページ)
👉 『シートン 4:タラク山の熊王(モナーク)』書評・感想:猟師と熊の壮大な追跡劇──アメリカ西部の大自然を描き切った名作漫画
アメリカ西部の大自然を舞台に、巨大な熊と猟師の長年にわたる攻防を描いた漫画。「追跡劇」の緊張感と旅情、そして動物への深いまなざしが繊細な筆致で描かれる。
『シートン 4:タラク山の熊王(モナーク)』(Amazonページ)




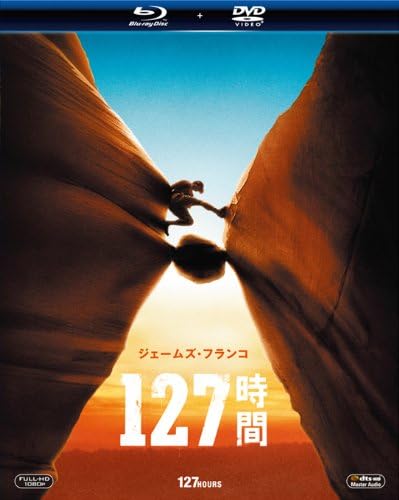

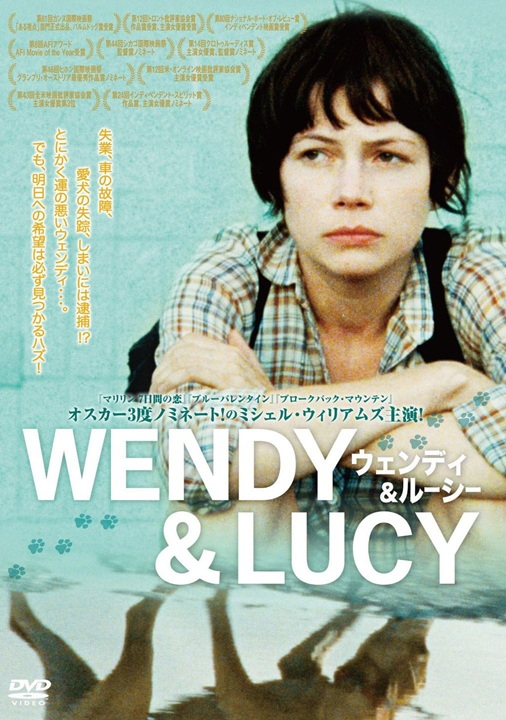





コメント